
そもそも、イールドカーブとは?
イールドカーブ(Yield curv)とは、利回り曲線のことです。
例えば下↓は2017年の日本国債のイールドカーブです。

債券などの利回りと残存期間の関係を表したものです。縦軸に利回り、横軸に残存期間をとります。
通常は、債券の利回りは残存期間が長くなるほど高くなります。したがってイールドカーブは右上がりの曲線になります。

では、逆イールドカーブとは?
では、逆イールドカーブとはなんでしょうか?
さきほぼみたとおりイールドカーブは右上がりの曲線です。
その「逆」ということで逆イールドカーブは右下がりの曲線のことを言います。
残存期間が長いほうが金利が低いと言うことです。つまり、長期金利が短期金利よりも低いことを表します。
過去の例をみると、逆イールドカーブ現象は幾度か発生しています。

短期金利は中央銀行が決める
では、金利とはどうやって決まるものなのでしょう。
実は、金利は中央銀行の政策の影響を大きくうけます。
特に短期金利は政策金利の強い影響をうけるためほぼほぼ中央銀行の思いのままです。

中央銀行は景気拡大局面では景気の過熱や物価上昇を抑制するために金利を引き上げ、景気縮小局面では景気の下支えのために金利を引き下げます。
一方で長期金利は短期金利の影響に加えて、将来の景気・物価の見通しや財政状況によって市場の見通し判断の影響をうけます。
市場が将来の景気や物価の見通しが上昇すると判断した場合は長期金利は上昇しますし、景気が悪化し物価が鈍ると判断した場合は下がることになるのです。

『日興アセットマネジメントより』
逆イールドカーブは何を表している?
さて、話を逆イールドカーブに戻します。
逆イールドカーブとは短期金利が長期金利よりも低いことなのですが、この状態って経済的にはどのように解釈すればいいのでしょうか。
短期金利が高い、つまり足元の景気が順調であることを表します。景気が過熱して、インフレになりやすく中央銀行は短期金利を上げざるおえないのです。
一方で、長期金利が下がっているということは市場関係者が将来の景気・物価の見通しが弱いとみているのです。
つまり、足元の景気は強いけど、将来の景気には不透明感がある状態というわけです。
逆イールドカーブは景気後退の兆候なのか?
では逆イールドカーブは景気後退の兆候なのでしょうか?
過去の歴史を紐解いてみましょう。

青線が長短金利差、赤線がNYダウ30になります。赤矢印↑が逆イールドカーブが発生したときになります。
なんとなくですが、逆イールドカーブが発生したときは株安、つまり景気後退の発生していることがわかります。
市場関係者の暗い景気の見通しが当たっているんですね。さすが市場です。すごいですね!
しかし、よくみてくださいね。
1998年に発生した逆イールドカーブでは株安が発生するまで2、3年のタイムラグがあるのがわかります。
株式相場は逆イールドカーブ発生後してからも株高が続き、その後のピークアウトするのですが逆イールドカーブ発生時の水準に戻った程度で落ち着いています。
つまり、逆イールドカーブが発生したからといって必ず売りが正解だったわけでもないようです。
特に市場は織り込みますので、逆イールドカーブが発生したらその後の株安の可能性も株価に織り込まれていきますからね。
もしかしたら、逆イールドカーブなんて、恐れることはないのかもしれません。

銀行は金利が低い短期資金を調達して、金利が高い長期資金を貸出しだすことでその利ざやを稼ぐのですが、長短金利が逆転すると利ざやをとれないため貸出を縮小させるためです。銀行の貸出の縮小が景気悪化をもたらすというわけです。
ミスターマーケットのノイズでした。
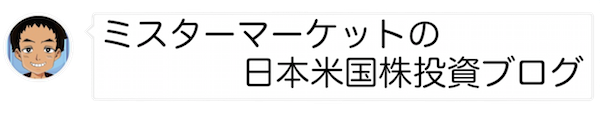

どうも、日米株投資家のミスターマーケットです。
今年2018年は米国金利上昇が株式市場を揺らしていますが、今回はそのなかで注目を浴びる「逆イールドカーブ」を取り上げます。
景気後退の兆候とも言われる逆イールドカーブですが、実際はどうなのか確認してみましょう。