
金融機関には金融商品の正しい説明が義務づけられている

さまざまな金融商品(たとえば保険など)を契約するとき、多くの説明を受け、何枚もの書面を確認させられ、サイン・捺印を求められることがあります。
今ではタブレットの画面をチョンチョンと押すだけの場合もありますが、それでもかなりの時間を費やすことになります。
金融機関のひとが親切丁寧にいろいろと教えてくれるのは良いのですが、面倒くさいこともあり、話半分に聞いて、簡単にサイン・捺印してしまったことがあるひとも多いのではないでしょうか?
ミスターマーケットも「はいはい」と思いながら、サイン・捺印することありますが、ふだん金融取引に慣れていない方はできればゆっくり確認しながら説明を受けることをオススメします。
金融機関の担当者も契約して欲しいと思っているわけですし、説明を求められたら、断る担当者はいないはずです。


書面にサイン・捺印するのは理解してから
金融機関には、消費者が知っておくべき情報や商品内容などを十分に説明することが法律に定められています。
例えば、元本割れのリスクがあるのか、あるとすれば具体的なリスク(例えば、株価変動リスク・金利変動リスク)の説明や、解約できる期間の制限・権利の行使の期間の制限の説明、手数料などのコストなどです。
また、重要な項目は内容を明記した書面を渡すことも義務づけられています。
さらに、金融機関は消費者にとって適切な金融商品であるかも考慮することとされており、たとえば、元本保証を望む消費者に元本割れの金融商品を販売できないこととされています(適合性の原則)。
もし、金融機関がこのような説明義務などを怠り、消費者に損失が発生したときは金融機関に損害賠償を求めることも法律上可能となっています。
ですので、金融商品の契約時に書面にいろいろとサイン・捺印を求められるのは、のちのち説明した・説明してないの争いを避けるためのものでもあるのです。
金融機関側からすれば、契約時の書面のサイン・捺印は僕たちは説明したという、金融機関側の証拠書類にすぎないわけで、金融商品の契約時の書面へのサインや捺印はかならず確認・理解・納得して行うことです。

だけど「投資は自己責任」ってことは変わらない

さきほど、金融機関が説明義務などを怠った場合は、金融機関に損害賠償を求めることができると書きました。確かにそれはそうなのです。
ただ、消費者(投資家)としては投資は自己責任であることはしっかり認識すべきだと思います。
おそらく金融機関がヘマして賠償責任が発生するような金融商品の販売はあまりあまりません。
書面等でのサイン・捺印で義務を果たした証拠をいろいろと残しているはずです。
僕たちができることは法律で金融機関に正しい説明が義務づけられていることを利用して、ゆっくり、わかるまで説明してもらうことです。
商品内容やリスクの可能性などしっかりとした説明を受け、そして、確認・理解・納得したあとに、購入するか自身で判断することが大切です。
もし、ちょっと腑におちないことがあるにも関わらず契約させられそうであれば「大切なことなので、家族で検討します」と伝えれば逃げることができます。一旦、中断して逃げてください。
その後、電話で、「家族に反対された」と言えばいいです。よい金融商品をよい金融機関から購入してください。

ミスターマーケットのノイズでした。
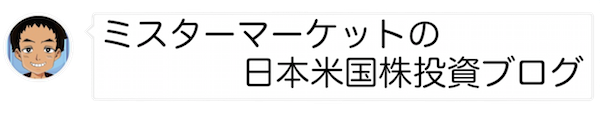

どうも、日米株投資家のミスターマーケットです。
今回はついつい騙されて金融商品を契約しないために覚えておきたいことを紹介します。